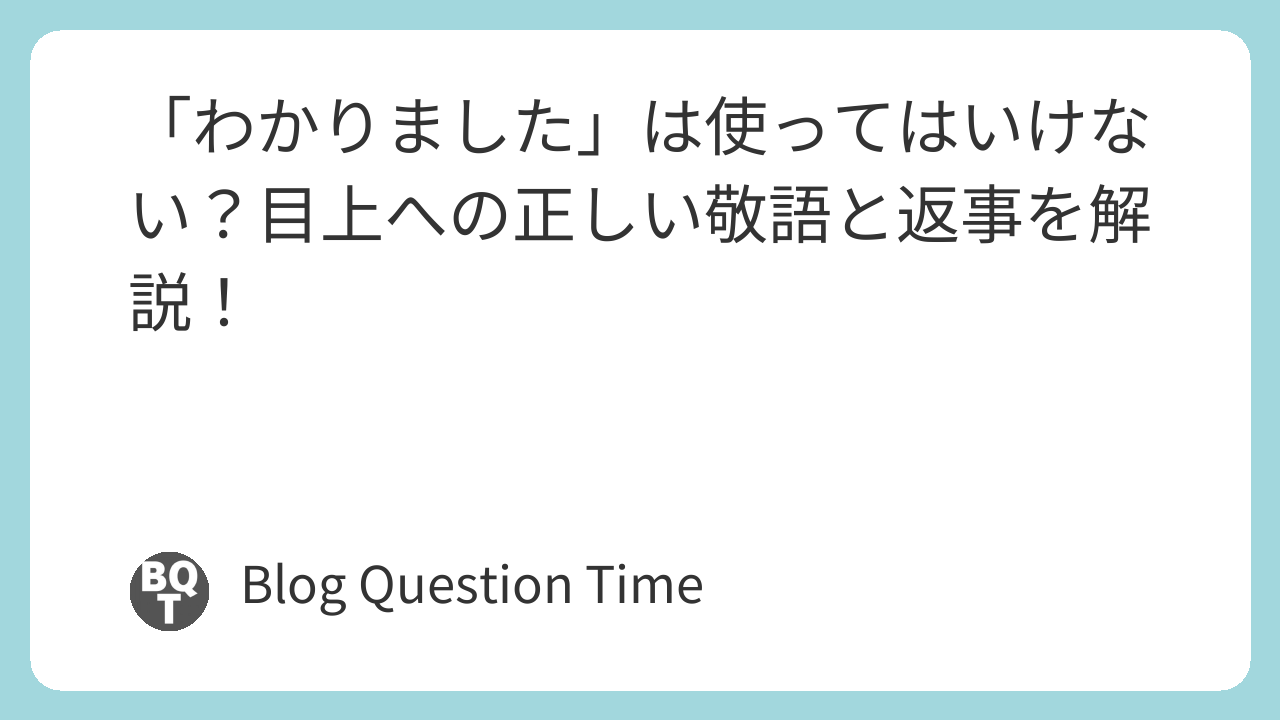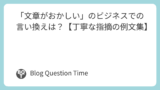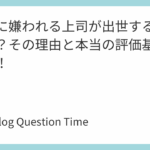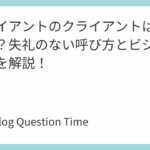上司からの指示や、取引先からの連絡に対して、「わかりました」と返事をしている方は多いのではないでしょうか。日常的に使われるこの言葉ですが、ふとした瞬間に、「『わかりました』って、敬語として本当に正しいのかな?」「もしかして、目上の方に使うのは失礼にあたるのでは?」と、その使い方に不安を感じたことはありませんか? この記事では、「わかりました」という言葉がビジネスシーンで「使ってはいけない」と言われる理由から、目上の方への適切な言い換え表現、そして状況に応じたスマートな使い方について、皆さんの疑問に寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。
言葉遣い一つで、相手に与える印象は大きく変わります。特に、承諾や理解を示す返事は、信頼関係を築く上で非常に重要な要素です。この記事を読めば、「わかりました」に関する疑問が解消され、自信を持って、より丁寧でプロフェッショナルなコミュニケーションが図れるようになるはずです。
なぜ「わかりました」は使ってはいけないと言われるのか?
まず、「わかりました」という言葉が、なぜビジネスシーン、特に目上の方に対して使うのが不適切とされるのか、その理由について見ていきましょう。
「わかりました」は正しい敬語だが、敬意が不足している
「わかりました」は、動詞「わかる」の連用形に、丁寧語の助動詞「ます」の過去形「ました」が付いた、文法的には正しい丁寧語です。
- しかし、敬意の度合いが低い:
- 丁寧語は、敬語の中でも最も基本的なものであり、相手を立てる「尊敬語」や、自分をへりくだる「謙譲語」と比較すると、敬意の度合いは高くありません。
- そのため、上司や取引先といった、特に敬意を払うべき相手に対して使うと、「敬意が不足している」「少し軽い」という印象を与えてしまう可能性があります。
- 子供っぽい、素人っぽい印象:
- 「わかりました」は、学生が先生に対して使うような、やや子供っぽい響きを持つと感じる人もいます。
- ビジネスのプロフェッショナルとして、より洗練された言葉遣いを身につけることが求められます。
「了解しました」と同様のニュアンス
「わかりました」と似た言葉に「了解しました」がありますが、これも目上の方に使うのは不適切とされています。
- 「了解」が持つ意味:
- 「了解」は、「物事を理解し、それを認める」という意味合いを持ちます。
- この「認める」という部分が、目上の方が目下の方に対して許可を与えるような、上から目線のニュアンスを含むと解釈されることがあります。
- 「わかりました」との共通点:
- 「わかりました」も、「理解した」という事実を単に伝えるだけの、やや一方的な印象を与える点では、「了解しました」と似ています。
これらの理由から、特にフォーマルなビジネスシーンでは、「わかりました」の使用は避けるのが無難とされています。
目上の方への正しい返事:「わかりました」の適切な言い換え表現
では、「わかりました」の代わりに、どのような言葉を使えば、敬意と理解の両方を伝えることができるのでしょうか。ビジネスシーンで頻繁に使われる、二つの重要な言い換え表現をマスターしましょう。
1. 「承知いたしました」:最も一般的で万能な表現
「承知いたしました」は、「わかりました」の最も代表的で、かつ万能な言い換え表現です。
- 「承知」の意味:
- 「承知」は、「事情を知ること、理解すること」に加え、「依頼や要求などを聞き入れること」を意味する謙譲語です。
- 「いたしました」:
- 「する」の謙譲語である「いたす」と、丁寧語の「ました」を組み合わせた、非常に丁寧な表現です。
- 使い方:
- 社内の上司から、社外の取引先まで、どのような相手にも使うことができます。
- 口頭でも、メールでも使用可能です。
- 例文:
- 「会議日程変更の件、承知いたしました。」
- 「ご指示いただいた内容、承知いたしました。早速、対応いたします。」
【つまずきやすいポイント】
「承知しました」という表現もありますが、「承知いたしました」の方が、より丁寧な印象を与えるため、目上の方や取引先に対しては「いたしました」を使うのがおすすめです。
2. 「かしこまりました」:より敬意の高い表現
「かしこまりました」は、「承知いたしました」よりも、さらに相手への敬意と、謹んで命令を受けるというニュアンスが強い表現です。
- 「かしこまる」の意味:
- 「目上の方の言うことを、敬って謹んで承る」という意味を持つ謙譲語です。
- 使い方:
- お客様や、特に高い敬意を示すべき相手からの依頼や命令に対して使います。
- 接客業や、秘書業務などで頻繁に使われる言葉です。
- 例文:
- (お客様からの注文に対し)「かしこまりました。Aセットでご用意いたします。」
- (社長からの指示に対し)「かしこまりました。本日中に資料を作成いたします。」
| 表現 | ニュアンスと使い方 | 主な使用シーン |
|---|---|---|
| 承知いたしました | 理解し、引き受ける。最も一般的で万能。 | 上司、取引先など、ビジネス全般 |
| かしこまりました | 謹んで承る。より高い敬意と服従のニュアンス。 | お客様、社長、特に敬意を払うべき相手からの依頼 |
3. その他の言い換え表現
状況によっては、さらに別の表現も有効です。
- 「承りました(うけたまわりました)」:
- 「聞く」「受ける」の謙譲語で、相手の要望や伝言などを「謹んでお受けします」というニュアンスが強いです。
- 例:「〇〇様からのご伝言、確かに承りました。」
- 「拝承いたしました(はいしょういたしました)」:
- 「承知いたしました」を、さらに硬く、改まった表現にしたものです。メールや文書で使われることがあります。
「わかりました」を使っても良い場面はある?
「わかりました」という言葉は、必ずしも全ての場面で禁止されているわけではありません。状況に応じた使い分けが重要です.
親しい先輩や同僚、後輩に対して
- 比較的カジュアルな関係性:
- 日常的な業務のやり取りの中で、親しい先輩や同僚、後輩に対して「わかりました」を使っても、失礼にあたることはほとんどありません。
- ただし、相手との関係性や、職場の雰囲気を考慮することが大切です。
「理解した」という事実をシンプルに伝えたい時
- 複雑な説明を受けた後など:
- 「なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。」のように、感謝の言葉と組み合わせることで、丁寧な印象を保ちつつ、理解したことを明確に伝えられます。
大切なのは、「わかりました」という言葉が持つ「ややカジュアルで、敬意の度合いが低い」というニュアンスを理解し、相手や状況に応じて、より適切な「承知いたしました」や「かしこまりました」と使い分ける意識を持つことです。
「わかりました」に関するよくある質問
「わかりました」という言葉の使い方について、皆さんが疑問に思われがちな点についてQ&A形式で解説します。ここでの情報が、皆さんの疑問を解消する一助となれば幸いです。
「わかりました」は失礼ですか?
目上の方や取引先に対して使うと、失礼な印象を与えてしまう可能性があります。「わかりました」は丁寧語ですが、敬意の度合いが低いため、ビジネスシーンでは「敬意が不足している」と受け取られることがあります。代わりに、「承知いたしました」や「かしこまりました」といった謙譲語を使うのが、ビジネスマナーとして推奨されます。
わかりました なぜだめ?
「わかりました」がダメ(不適切)とされる主な理由は、敬意の度合いが低く、子供っぽい、あるいは軽い印象を与えてしまう可能性があるからです。また、「理解した」という事実を伝えるだけで、相手の指示を「謹んで受ける」という謙虚な姿勢が伝わりにくいため、ビジネスのプロフェッショナルとしては、より敬意の高い「承知いたしました」などを使うべき、とされています。
「了解しました」と「わかりました」の違いは何ですか?
「了解しました」と「わかりました」は、どちらも「理解した」という意味では共通していますが、ニュアンスに違いがあります。
- 了解しました: 「理解し、承認する」という意味合いが強く、目上の方が目下の方に許可を与えるようなニュアンスを含むため、上司などに使うのは不適切とされます。
- わかりました: 単に「理解した」という事実を伝える丁寧語です。
どちらも目上の方への返事としては不適切とされることが多いため、ビジネスシーンでは「承知いたしました」を使うのが最も安全です。
面接で「わかりました」はダメですか?
面接というフォーマルな場では、「わかりました」の使用は避けた方が賢明です。面接官からの説明や質問に対しては、「はい、承知いたしました」や「はい、かしこまりました」と返事をすることで、ビジネスマナーを正しく理解している、丁寧で礼儀正しい人物であるという印象を与えることができます。「わかりました」と言ってしまったからといって、即不合格になるわけではありませんが、より適切な敬語を使えるに越したことはありません。
まとめ
「わかりました」という言葉は、文法的には正しい丁寧語ですが、ビジネスシーン、特に目上の方や取引先に対して使うと、敬意が不足している、あるいは子供っぽい印象を与えてしまう可能性があるため、「使ってはいけない」とされています。
「わかりました」の代わりに、相手への敬意と、指示や依頼を謹んで受け入れる姿勢を示すことができる、以下の謙譲語表現を使うのがビジネスマナーとして適切です。
- 承知いたしました: 最も一般的で、社内外問わず、どのような相手にも使える万能な表現。
- かしこまりました: お客様や、特に高い敬意を示すべき相手からの依頼に対して使う、より丁寧な表現。
「わかりました」と「了解しました」は、どちらも目上の方への返事としては不適切とされることが多いです。これらの言葉の正しい意味と使い分けを理解し、状況に応じて自然に「承知いたしました」や「かしこまりました」が使えるようになることが、信頼されるビジネスパーソンへの第一歩です。
この記事を通じて、「わかりました」の使い方に関する疑問が解消され、ご自身のビジネスコミュニケーションに自信を持てるようになる一助となれば幸いです。