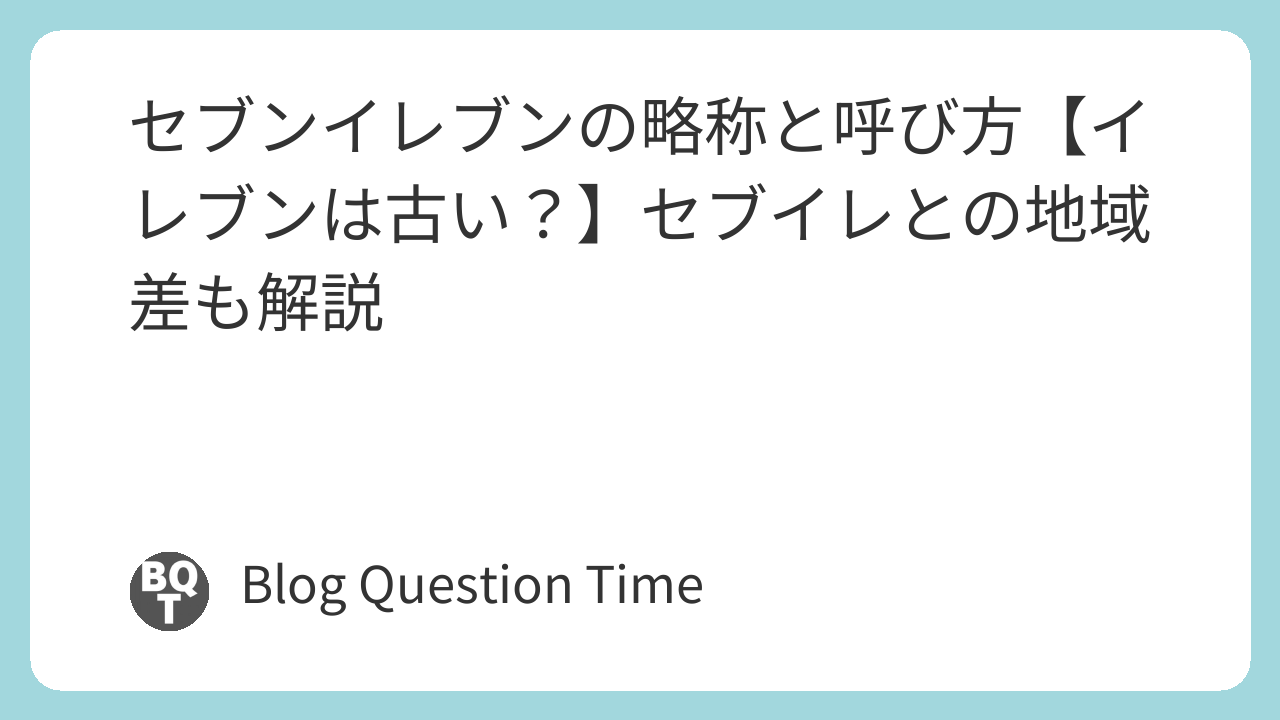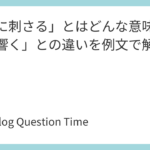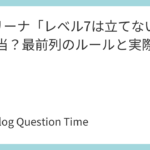「セブンで飲み物買ってきて」
「そこのセブイレで待ち合わせしよう」
ふと気になるセブンイレブンの呼び方。「セブン」が当たり前だと思っていたら、関西出身の友達が「セブイレ」と言っていて驚いた…なんて経験はありませんか?あるいは、親世代が「イレブン」と呼んでいるのを聞いたことがあるかもしれません。
一体どの略称が多数派で、地域によって本当に違いはあるのでしょうか?
この記事では、全国のアンケート調査やSNSでの使われ方を基に、セブンイレブンの略称・呼び方の謎を徹底解説します。あなたの呼び方は多数派?それとも少数派?その答えがきっと見つかります。
【全国調査】セブンイレブンの略称、多数派は「セブン」
まず、現在の全国的な傾向を見てみましょう。
様々な調査で共通しているのは、セブンイレブンの略称として最も多く使われているのは「セブン」であるという事実です。
特に10代〜30代の若い世代や、関東圏では「セブン」と呼ぶ人が圧倒的多数を占めています。短くて言いやすい「セブン」が、現代のコミュニケーションにおいて最もスタンダードな呼び方と言えるでしょう。
やはり本当だった!関東「セブン」vs 関西「セブイレ」の地域差
全国的には「セブン」が優勢ですが、地域に目を向けると、はっきりとした違いが見えてきます。
関東圏:「セブン」が圧勝
東京を中心とする関東圏では、略称として「セブン」が広く浸透しており、「セブイレ」と呼ぶ人はごく少数です。「コンビニといえばセブン」という感覚で、自然と「セブン」という呼び方が定着したと考えられます。
関西圏:なぜ「セブイレ」と呼ぶのか?その理由を探る
一方、大阪、京都、兵庫などの関西圏では「セブイレ」という略称が根強く使われています。これにはいくつかの説があります。
- 音のリズム説: 関西弁のイントネーションでは、「セブン」よりも「セブイレ」の方がリズムよく発音しやすいという説。
- 4文字略称の文化説: 「マクドナルド→マクド」「ファミリーマート→ファミマ」のように、関西では4文字に略す文化があり、「セブンイレブン」も「セブイレ」と4文字にまとめるのが自然だったという説。
- 区別説: 7チャンネルのテレビ局を「セブン」と呼ぶ習慣があったため、区別するために「セブイレ」が定着したという説。
明確な理由は一つではありませんが、関西では「セブイレ」が独自の文化としてしっかりと根付いていることは間違いありません。
その他の地域(東海・九州・北海道など)での呼び方は?
東海地方や九州、北海道などの地域では、関東と同様に「セブン」と呼ぶ人が多い傾向にあります。ただし、関西に近い地域や、関西出身者が多い地域では「セブイレ」も通じるなど、エリアによって混在しているようです。
「イレブン」と呼ぶのは少数派?世代による違い
クリックが発生しているキーワード「イレブン」という呼び方はどうなのでしょうか?
昔は「イレブン」呼びも存在した?
現在40代以上の世代の中には、若い頃「イレブン」と呼んでいた、あるいは周りにそう呼ぶ人がいた、という方もいるかもしれません。セブンイレブンが日本に登場した初期には、名称の後半部分を取って「イレブン」と略す人も一定数存在しました。
なぜ全国的に「セブン」が主流になったのか
しかし、テレビCMなどで「セブン、イレブン、いい気分」というキャッチフレーズが広まると、「セブン」という部分が強く印象付けられました。その結果、言いやすさも相まって、徐々に「セブン」が全国的な主流の座を獲得していったと考えられます。
現在では、「イレブン」という呼び方は地域差というより「世代差」や「過去の呼び方」と捉えるのが適切でしょう。
「ブンブン」「セブレ」?SNSで見かける少数派の面白い略称
主流の「セブン」「セブイレ」以外にも、SNSなどではユニークな略称が生まれています。
- ブンブン: 「セブンイレブン」の真ん中部分を取った斬新な略称。
- セブレ: こちらもSNSの一部で使われることがある呼び方。
- SEJ: 公式なアルファベット略称(Seven-Eleven Japanの頭文字)。
これらは非常に少数派ですが、友人同士の会話などで使ってみると面白いかもしれません。
なぜ?他のコンビニ略称(ファミマ等)に地域差がない理由
ここで一つの疑問が浮かびます。「ファミリーマート」は全国的に「ファミマ」なのに、なぜセブンイレブンだけ地域差が生まれたのでしょうか?
これは、「ファミリーマート」や「ローソン」の略し方が「ファミマ」以外に考えにくいのに対し、「セブンイレブン」は「セブン」と「セブイレ」という二つの有力な略し方が存在したため、地域によってどちらが定着するかが分かれた、と考えるのが自然です。
よくある質問
Q. セブンイレブンの公式な略称はありますか?
A. セブン-イレブン・ジャパンとしての公式な略称は定められていません。ただし、株式市場などで使われるアルファベットでの略称は「SEJ」です。
Q. ロゴの「n」だけ小文字なのはなぜですか?
A. これには「商標登録の際に、デザイン性を出すためだった」という説や、「”ELEVEN”と全て大文字だと印象が強すぎるため、最後のnを小文字にして見た目を和らげた」という説など、諸説あります。公式に理由は明言されていませんが、デザイン上の工夫であることは間違いないようです。
Q. そもそもセブンイレブンという名前の由来は?
A. もともとアメリカで誕生したセブンイレブンが、創業当時に「朝7時から夜11時まで」営業していたことに由来します。当時としては画期的に長い営業時間だったため、それをそのまま店名にしました。
まとめ
セブンイレブンの略称・呼び方の謎、いかがでしたか?
- 全国的な多数派: 「セブン」
- 地域差: 関東では「セブン」、関西では「セブイレ」が主流。
- 世代差: かつて使われた「イレブン」は、今では少数派。
あなたの呼び方は、住んでいる地域や世代の文化を反映しているのかもしれません。次に誰かが違う呼び方をしていても、「ああ、あの地域の人なのかな」と思いを馳せると、少し面白い発見があるかもしれませんね。