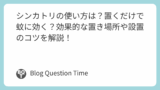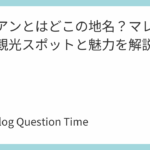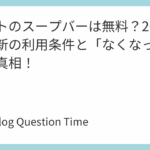TikTokを眺めていると、「界隈診断」というフィルターで「あなたは事後界隈です」と表示されたり、ハッシュタグで「#事後界隈」という投稿を目にしたりして、「『事後界隈』って、一体どういう意味?」「もしかして、何か悪い意味なの?」と、その謎の言葉に戸惑った経験はありませんか? この記事では、TikTokを中心に流行している「事後界隈」という言葉の正しい意味と読み方、その流行のきっかけとなった元ネタ、そしてSNSでの具体的な使い方まで、皆さんの疑問に寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。
ネットスラングや新しいトレンドワードは、その意味や背景を知らないと、コミュニケーションの中で戸惑ってしまうこともありますよね。この記事を読めば、「事後界隈」に関する疑問が解消され、TikTokやSNSでの会話を、もっと安心して楽しめるようになるはずです。
「事後界隈」とは?TikTokで流行する謎の言葉
まず、「事後界隈」という言葉が、どのような意味で使われているのか、そしてなぜ今、TikTokで話題になっているのかを見ていきましょう。
「事後界隈」の基本的な意味と読み方
「事後界隈」とは、特定の出来事(ライブ、イベント、アニメの放送など)が終わった後に、その感想や考察で盛り上がるファンの集まり(コミュニティ)を指すネットスラングです。
- 読み方:
- じごかいわいと読みます。
- 言葉の成り立ち:
- 事後(じご): 物事が終わった後のこと。
- 界隈(かいわい): 共通の趣味や関心を持つ人々の集まりやコミュニティを指す言葉。
- 組み合わせた意味:
- 特定のイベントなどが終了した後に、その体験を共有したり、関連する話題で盛り上がったりする、一時的な、または熱量の高いファンの集まりを指します。
- 例:「ライブの事後界隈で、セットリストについて熱く語り合おう」
なぜ今、TikTokで話題になっているのか?
「事後界隈」という言葉がTikTokで急速に広まった背景には、特定の機能の存在が大きく関係しています。
- 「界隈診断」フィルターの登場:
- TikTokには、ユーザーの顔や雰囲気をAIが分析し、「あなたは〇〇界隈です」と自動で診断してくれる「界隈診断」というエフェクト(フィルター)があります。
- この診断結果の中に、他の「天使界隈」「地雷系界隈」といった言葉と並んで、ランダムに「事後界隈」という言葉が表示されることがあります。
- 「謎ワード」としての拡散:
- 多くのユーザーにとって、「事後界隈」は聞き慣れない言葉であったため、「これってどういう意味?」「なんで私が事後界隈なの?」といった戸惑いや好奇心から、この言葉がSNS上で急速に拡散しました。
- つまり、言葉そのものの意味よりも、「界隈診断」という流行のフィルターに登場する謎の言葉として、まず話題になったのです。
【つまずきやすいポイント】「事後界隈」の元ネタと流行のきっかけ
「事後界隈」という言葉の流行を理解する上で、つまずきやすいのが「元ネタ」と「言葉が持つ二重の意味」です。
発端は「界隈診断」フィルター
前述の通り、TikTokでの流行の直接的な元ネタは、「界隈診断」というエフェクト(フィルター)です。
- 診断結果のランダム性:
- このフィルターは、科学的な根拠に基づいて診断しているわけではなく、あくまでエンターテイメントとして、ランダムに結果を表示するものです。
- そのため、表示された「事後界隈」という結果に、深い意味はありません。
- ユーザーの反応:
- 多くのユーザーは、この謎の診断結果を面白がり、「#事後界隈」というハッシュタグを付けて、自身の診断結果動画を投稿しました。
- これが、「事後界隈」という言葉の認知度を一気に高めるきっかけとなりました。
「事後」という言葉が持つインパクトと誤解
「事後界隈」という言葉がこれほどまでに注目を集めたもう一つの理由は、「事後」という言葉が持つ、やや意味深な響きにあります。
- 本来の意味:
- 「事後」は、単に「物事が終わった後」を指す一般的な言葉です。(例:「事後報告」)
- 連想される別の意味:
- 一方で、「事後」という言葉は、男女間の性的な行為の後を指す隠語として使われることもあります。
- このため、「界隈診断」で「事後界隈」と表示されたユーザーが、「もしかして、そういう意味…?」と戸惑ったり、面白がったりしたことが、さらなる拡散に繋がりました。
- TikTokでの文脈:
- しかし、TikTokの「界隈診断」における「事後界隈」は、この性的な意味合いを意図したものではありません。
- あくまで、「イベント後のファンの集まり」という、本来のネットスラングとしての意味か、あるいは単にランダムに表示された無意味な言葉と捉えるのが適切です。
「事後界隈」の具体的な使い方と関連する投稿
では、実際に「事後界隈」という言葉は、SNSでどのように使われているのでしょうか。
SNS(TikTok)での使い方と例文
- 界隈診断の結果報告として:
- 最も多いのが、界隈診断フィルターを使った動画投稿です。
- 例文:「界隈診断やってみたら、まさかの事後界隈だったんだけどww どういう意味?」
- イベント後の感想共有として:
- 本来の意味である、イベント後のファンコミュニティを指して使われます。
- 例文:「昨日のライブ最高だった!これから事後界隈でみんなの感想見てこよう。」
- 言葉遊びとして:
- 「事後」という言葉の持つ二重の意味を、ジョークとして使うケースです。
- 例文:「今日のテスト、完全に爆死した…もう気分は事後界隈だわ…(終わってる、の意)」
投稿されている「事後界隈」の写真や動画の傾向
「#事後界隈」で検索すると、様々な写真や動画が投稿されていますが、その内容は主に以下の二つに大別されます。
- 界隈診断の動画:
- 多くのユーザーが、自身の顔に「事後界隈」という診断結果が表示された動画を投稿しています。
- 言葉のイメージに基づく投稿:
- 「事後」という言葉の持つ、少しアンニュイで、物憂げな雰囲気を表現した写真や動画。
- 例えば、夕暮れの風景や、少し気だるそうな表情の自撮りなど、直接的な意味とは関係なく、言葉の響きから連想されるイメージを表現した投稿が見られます。
「事後界隈」に関するよくある質問
「事後界隈」や、関連する「界隈」という言葉について、皆さんが疑問に思われがちな点についてQ&A形式で解説します。ここでの情報が、皆さんの疑問を解消する一助となれば幸いです。
「事後ってる」とはどういう意味ですか?
「事後ってる(じごってる)」とは、「事後界隈」から派生した、さらに新しいスラングです。明確な定義はありませんが、文脈によって以下のような意味で使われることが多いようです。
- 燃え尽きている、終わっている: イベントなどが終わってしまい、燃え尽き症候群のようになっている状態。あるいは、何か大きな失敗をして、呆然としている状態。
- アンニュイな、気だるい雰囲気: 「事後」という言葉のイメージから、少し気だるそうで、物憂げな雰囲気をしている様子。
オタク用語で「○○界隈」とは何ですか?
オタク用語(ネットスラング)における「〇〇界隈」とは、共通の趣味や、応援している対象(推し)、価値観を持つ人々の集まりやコミュニティを指します。
- 例:
- 「ジャニオタ界隈」(ジャニーズのファン)
- 「ゲーム実況界隈」(ゲーム実況者が好きな人たち)
- 「自撮り界隈」(自撮り写真をSNSに投稿する文化を持つ人たち)
元々は「そのあたり一帯」を指す言葉でしたが、SNSの普及に伴い、物理的な場所ではなく、人々の繋がりやコミュニティを指す言葉として広く使われるようになりました。
「何界隈ですか?」の意味は?
「何界隈ですか?」と尋ねられた場合、それは「あなたは、どのような趣味やコミュニ-ティに属していますか?」「普段、どのようなジャンルに興味がありますか?」という意味の質問です。
初対面の相手との会話で、共通の話題を見つけるためのきっかけとして使われることが多い、現代的なコミュニケーションの一つです。
何 界隈 って何?
上記の質問と同様に、「何界隈?」と聞かれたら、それはあなたの所属するコミュニティや、趣味のジャンルを尋ねられています。ご自身の好きなものや、普段よく見ているコンテンツなどを答えると、会話が弾むでしょう。
例えば、「私は〇〇っていうアイドルの界隈にいます」や、「最近は△△っていうアニメの界隈で活動してます」といったように答えます。
まとめ
「事後界隈(じごかいわい)」とは、もともとは特定の出来事(ライブ、イベントなど)が終わった後に、その感想や考察で盛り上がるファンのコミュニティを指すネットスラングです。
しかし、近年TikTokで急速に広まった背景には、ユーザーの顔を診断する「界隈診断」フィルターの存在が大きく関係しています。この診断結果としてランダムに「事後界隈」と表示されることが、言葉の認知度を一気に高めました。
「事後」という言葉が持つ、やや意味深な響きから、様々な憶測やジョークが飛び交っていますが、TikTokの文脈においては、深刻な意味合いはなく、「界隈診断に登場する謎の言葉」として、一種のミーム(ネタ)として楽しまれているのが実情です。
この記事を通じて、「事後界隈」という言葉の正しい意味、流行の元ネタ、そして具体的な使い方についての疑問が解消され、SNSのトレンドをより深く、そして安心して楽しめるようになる一助となれば幸いです。