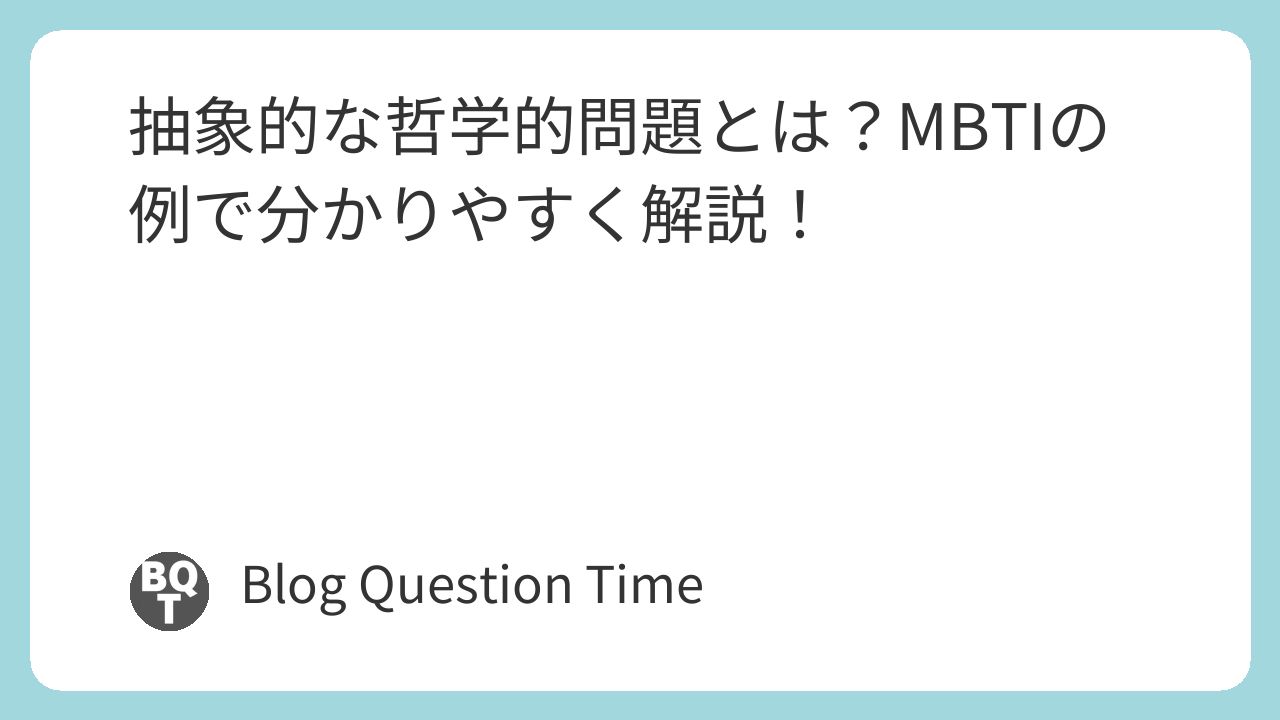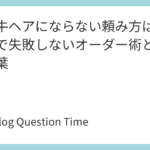MBTI診断を受けていると、時々「抽象的な哲学的問題についてじっくり考える」といった、少し変わった質問項目を目にすることがありますよね。「『抽象的な哲学的問題』って、一体どういう意味?」「なんだか難しそう…」と、その言葉の意味が分からず、戸惑ってしまった経験はありませんか? この記事では、そんな「抽象的な哲学的問題」という言葉の正しい意味と読み方から、「本当の自分とは?」といった身近な具体例、そしてなぜMBTI診断などでこのような問いがされるのかまで、皆さんの疑問に寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。
哲学と聞くと、難しくて縁遠い学問のように感じるかもしれません。しかし、実は私たちの日常生活の中に、哲学的な問いのヒントはたくさん隠されています。この記事を読めば、「抽象的な哲学的問題」に関する疑問が解消され、ご自身の思考の癖や、物事を深く考えることの面白さに気づけるようになるはずです。
「抽象的な哲学的問題」とは?分かりやすく解説
まず、「抽象的な哲学的問題」という言葉が、どのような意味で使われているのか、その言葉を分解しながら見ていきましょう。
「抽象的」と「哲学的問題」それぞれの意味
この言葉は、「抽象的」と「哲学的問題」という二つの要素から成り立っています。
- 抽象的(ちゅうしょうてき)とは:
- 個別の、具体的な物事から離れて、それらに共通する性質や本質を抜き出して考えることです。
- 例えば、目の前にある「赤いリンゴ」や「赤いポスト」という具体的なものから、「赤色とは何か?」という共通の性質について考えるのが、抽象的な思考です。
- 哲学的問題(てつがくてきもんだい)とは:
- 「〇〇とは何か?」という、物事の根本的な意味や本質を問うような、簡単には答えが出ない問題のことです。
- 科学のように、実験や観察で一つの正解を導き出せるものではありません。
これらを組み合わせた「抽象的な哲学的問題」とは、具体的な事例や事実に直接依存せず、物事の根本的な原理や本質を問うような、答えが一つに定まらない問いのことを指します。
なぜMBTI診断などで問われるのか?
では、なぜMBTI診断のような性格診断で、このような問いがされるのでしょうか。
- 思考の癖と思考タイプを知るため:
- MBTI診断では、人が情報をどのように認識し、どのように判断を下すか、という思考のプロセスを分析します。
- 「抽象的な哲学的問題」に対して、「じっくり考えるのが好きだ」と答えるか、「考えても時間の無駄だと思う」と答えるかによって、その人が物事を概念的に捉えるタイプ(N型:直観型)なのか、それとも具体的・現実的に捉えるタイプ(S型:感覚型)なのか、といった思考の癖を見極めるための一つの指標としているのです。
【つまずきやすいポイント】抽象的な哲学的問題の具体例
「抽象的な哲学的問題」という言葉だけでは、まだピンとこないかもしれません。ここでは、身近な例を交えながら、具体的にどのような問いがあるのかを見ていきましょう。
例えばどんな問い?身近な例で理解する
哲学的な問いは、私たちの日常生活の中にたくさん隠されています。
存在に関する問題:「本当の自分とは?」
- 問い: 「本当の自分って、どこにあるんだろう?」「周りに合わせて行動している自分と、一人でいる時の自分、どっちが本当の自分?」
- 解説: これは、「自己同一性」に関する哲学的な問いです。私たちは、場所や相手によって様々な役割(学生、会社員、友人、家族など)を演じますが、その根底にある「変わらない自分」とは一体何なのか、という根源的な問いです。
知識に関する問題:「リンゴは本当に赤いのか?」
- 問い: 「私たちは皆、このリンゴを『赤い』と見ているけれど、もしかしたら人によって見えている『赤色』は違うのかもしれない。だとしたら、『リンゴが赤い』という事実は、本当に存在するのだろうか?」
- 解説: これは、「クオリア」に関する哲学的な問いです。他人が見ている「赤」を、自分自身が体験することはできません。私たちが「知っている」と思っていることが、本当に客観的な真実なのかを問うものです。
倫理に関する問題:「トロッコ問題」
- 問い: 「暴走するトロッコの先に5人の作業員がいる。あなたがポイントを切り替えれば、5人は助かるが、代わりに切り替えた先の線路にいる1人が犠牲になる。あなたは何もしないべきか、それとも1人を犠牲にして5人を助けるべきか?」
- 解説: これは、倫理学における有名な思考実験です。「より多くの命を救うべきだ」という功利主義的な考えと、「誰かの命を意図的に奪うべきではない」という義務論的な考えが対立する、非常に悩ましい問題です。
哲学的問題と科学的な問題の違い
哲学的問題と科学的な問題は、その問いの性質が異なります。
| 項目 | 哲学的問題 | 科学的な問題 |
|---|---|---|
| 問いの性質 | 「〇〇とは何か?」「どうあるべきか?」 | 「〇〇はどうなっているか?」「なぜそうなるか?」 |
| 答えの求め方 | 思考、対話、論理的推論 | 観察、実験、データ分析 |
| 答えの数 | 答えは一つに定まらないことが多い | 原則として、一つの客観的な真実を目指す |
例えば、「人間とは何か?」と問うのが哲学であり、「人間の体はどのように機能しているか?」と問うのが科学です。
なぜ「時間の無駄だと思う」と感じる人がいるのか?
「抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う」という感覚は、決して珍しいものではありません。なぜ、そう感じてしまうのでしょうか。
答えのない問いへの向き合い方
- 実用性の観点:
- 哲学的な問いは、多くの場合、日々の生活や仕事に直接的な利益をもたらしません。「幸福とは何か?」と考えても、明日のお給料が増えるわけではありません。
- 実用性や、具体的な成果を重視する人にとっては、「考えても意味がない」「時間の無駄だ」と感じるのは、ごく自然なことです。
- 思考のプロセスの違い:
- 明確な答えや、白黒はっきりした結論を求める人にとって、答えが一つに定まらない哲学的な問いは、思考の迷路に迷い込むような、居心地の悪いものに感じられることがあります。
思考タイプの違い(MBTIとの関連)
前述の通り、MBTI診断では、このような思考の傾向をタイプ分けの一つの指標としています。
- S型(感覚型):
- 現実的で、具体的、実用的な情報を重視する傾向があります。
- 「今、ここにある事実」を基に物事を考えるため、抽象的な概念や、仮定の話にはあまり興味を示さないことがあります。
- N型(直観型):
- 物事の背景にある意味や、将来の可能性、全体像といった、抽象的な情報を捉えるのが得意な傾向があります。
- 「なぜ?」「もし~だったら?」と、物事の本質や可能性について考えることを好みます。
どちらの思考タイプが優れているというわけではなく、これは単なる思考の癖の違いです。「時間の無駄だ」と感じることも、一つの自然な思考スタイルと言えるでしょう。
抽象的な哲学的問題に関するよくある質問
抽象的な哲学的問題について、皆さんが疑問に思われがちな点についてQ&A形式で解説します。ここでの情報が、皆さんの疑問を解消する一助となれば幸いです。
「抽象的な」とはどういう意味ですか?
「抽象的な」とは、個別の、具体的な物事から離れて、それらに共通する性質や本質を抜き出して考えることを指します。例えば、具体的な「犬」や「猫」から離れて、「動物とは何か?」という共通の概念について考えるのが抽象的な思考です。
哲学的な問いの例は?
哲学的な問いの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 「私たちはなぜ存在するのか?」
- 「幸福とは何か?」
- 「善と悪の基準はどこにあるのか?」
- 「意識とは何か?」
- 「時間とは何か?」
これらの問いは、科学だけでは答えが出せず、古くから多くの哲学者たちが考え続けてきた根源的な問題です。
「抽象的な議論」とはどういう意味ですか?
「抽象的な議論」とは、具体的な事例やデータに基づかず、概念や理念、あるいは一般論だけで進められる議論のことです。時に、「机上の空論で、現実的ではない」といったネガティブなニュアンスで使われることもあります。しかし、物事の根本的な方針や理念を決める上では、抽象的な議論も非常に重要です。
「哲学的な」とはどういう意味ですか?
「哲学的な」とは、物事の根源や本質について、深く、多角的に考えるさまを指します。例えば、単に出来事を受け入れるだけでなく、「なぜそうなったのか」「その本当の意味は何か」と問い続ける態度が「哲学的」と言えます。
まとめ
「抽象的な哲学的問題」とは、具体的な事例に直接依存せず、物事の根本的な原理や本質を問うような、答えが一つに定まらない問いのことです。MBTI診断などでこの質問が出てくるのは、その人が物事を概念的に捉えるタイプか、それとも現実的に捉えるタイプか、といった思考の癖を見極めるための一つの指標としてです。
「本当の自分とは?」「幸福とは何か?」といった問いがその具体例であり、科学のように実験で一つの答えを出せるものではありません。
「考えても時間の無駄だ」と感じる人がいるのは、実用的な成果を重視したり、明確な答えを求める思考スタイルを持っていたりするためで、それは思考の癖の違いによる自然な反応です。
この記事を通じて、「抽象的な哲学的問題」という言葉の意味、その具体例、そしてなぜそのような問いがされるのかについての疑問が解消され、ご自身の思考の特性や、物事を深く考えることの面白さに気づくきっかけとなれば幸いです。