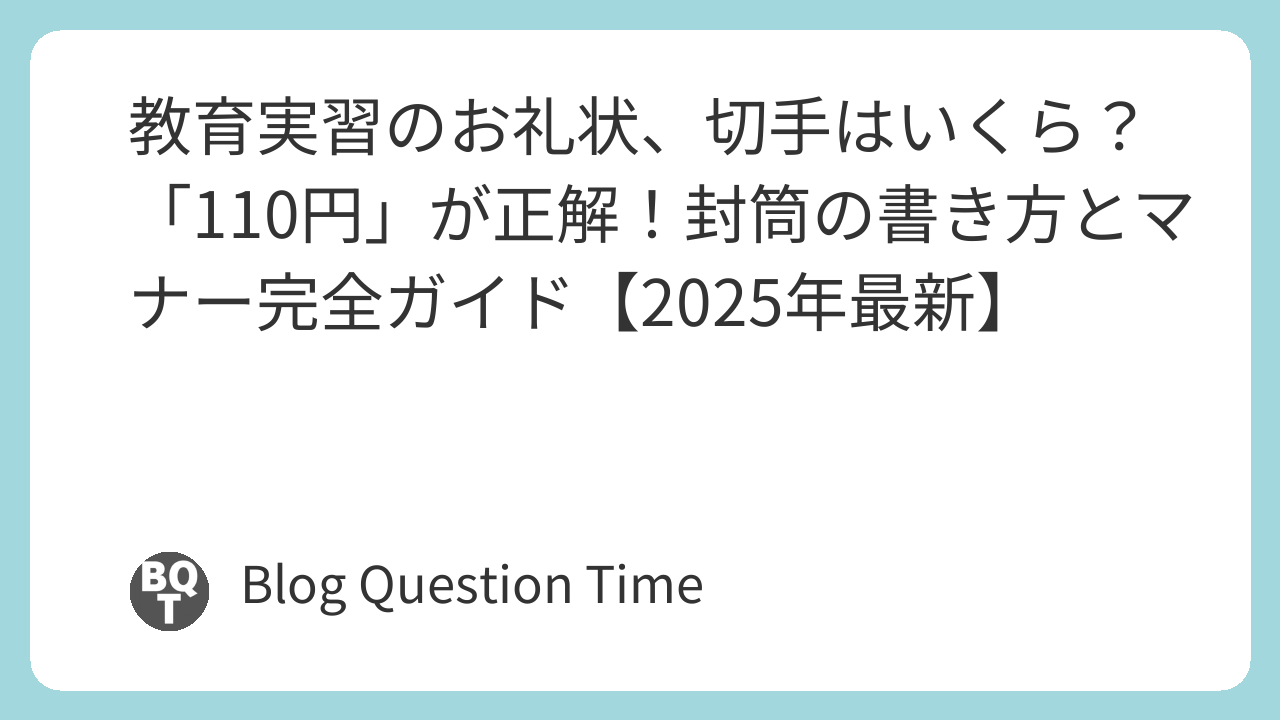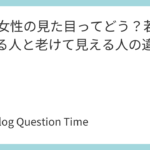数週間の教育実習を終え、お世話になった先生方や生徒たちへの感謝を伝えるために書くお礼状。いざ準備を始めると、「あれ?切手って84円だっけ?」「封筒の書き方はこれで合ってる?」と、手紙のマナーに自信が持てなくなることはよくあります。
特に注意が必要なのが、郵便料金です。2024年秋の大幅な料金改定により、以前の常識は通用しなくなっています。料金不足で相手先に届いてしまうのは、実習生として最も避けたい失敗の一つです。
この記事では、2025年現在の最新郵便料金に基づいた切手代の正解から、教育実習のお礼状としてふさわしい切手の選び方、そして好印象を与える封筒の書き方までを徹底解説します。迷わず、自信を持って感謝の気持ちを届けましょう。
【2025年最新】教育実習のお礼状、切手代は「110円」
結論からお伝えします。教育実習のお礼状を送る場合、貼るべき切手の料金は「110円」です。
84円は昔の話!郵便料金改定のポイント
以前は「定形郵便物(25g以内)」であれば84円で送れましたが、2024年10月の郵便料金改定により、封書(定形郵便物)の基本料金は110円に値上げされました。
もし、実家の引き出しにあった古い84円切手をそのまま貼って出してしまうと、26円の料金不足となります。
- 差出人に戻ってくる: まだマシなケースですが、出し直しとなり到着が遅れます。
- 相手に不足分を払わせる: 最悪のケースです。お世話になった実習校に「26円払ってください」と郵便局員が請求することになり、大変な失礼にあたります。
必ず「110円分」の切手が貼られているか確認しましょう。
「50gまで一律110円」だから便箋が増えても安心
値上げは痛手ですが、メリットもあります。以前は「25g以内」と「50g以内」で料金が分かれていましたが、現在は「50g以内なら一律110円」に統合されました。
一般的な便箋と封筒の重さは以下の通りです。
- 封筒(長形4号):約3〜4g
- 便箋(B5サイズ):1枚約3〜4g
つまり、便箋が5〜6枚になっても、写真などを数枚同封しても、50gを超えることはまずありません。
「枚数が増えたから料金が変わるかも?」と心配する必要はなく、安心して110円切手を貼ってください。
重さが不安なら「家庭用はかり」か「郵便局窓口」へ
それでも「厚手の紙を使ったから心配」「文集などを同封したい」という場合は、重さを確認するのが確実です。
- 家庭用はかり(キッチンスケール): 50g以内であることを確認できればOKです。
- 郵便局の窓口: その場で重さを量り、正確な料金を教えてくれます。切手もその場で購入・貼付できるので、最も安全な方法です。
お礼状にふさわしい切手の種類と選び方
料金は110円で決まりましたが、どんなデザインの切手を貼るかによって、相手に与える印象は変わります。
ベストは「記念切手・特殊切手(花や風景)」
お礼状として最も好印象なのは、季節の花や美しい風景などが描かれた「記念切手(特殊切手)」です。
郵便局の窓口に行けば、様々なデザインの110円切手が販売されています。
- 春: 桜やタンポポ
- 秋: 紅葉やコスモス
など、実習を行った季節や、送る時期に合わせたデザインを選ぶと、「細やかな気配りができる学生だな」という印象を与えられます。
普通切手でもOK?キャラクターものはNG?
- 普通切手: コンビニなどで売っている一般的な切手です。これを使ってもマナー違反ではありません。シンプルで清潔感があれば十分です。
- キャラクターもの: ディズニーやアニメなどのキャラクター切手は、親しい間柄なら良いですが、教育実習のお礼状というフォーマルな場面には不向きです。避けたほうが無難でしょう。
- 慶事用切手(扇の柄など): これは結婚式の招待状などに使うものなので、お礼状には使いません。
コンビニで110円切手が売っていない時の対処法
「夜に急いでコンビニで切手を買おうとしたら、110円切手が置いていなかった」というケースも考えられます。
コンビニによっては需要の少ない高額切手を置いていないことがあります。
その場合の対処法は2つです。
- 複数の切手を組み合わせる:
- 例:63円切手+47円分の切手(※ぴったりにするのが難しいため非推奨)
- ただし、お礼状の封筒に切手をベタベタと複数枚貼るのは、見た目が美しくありません。できるだけ1枚ですっきり貼るのがマナーです。
- 翌日、郵便局に行く:
- 多少の手間でも、郵便局が開いている時間に窓口へ行き、きれいな110円切手を買うことを強くおすすめします。
失敗しない「封筒」の選び方と書き方マナー
中身が立派でも、封筒の書き方が雑だと印象は台無しです。基本を押さえましょう。
封筒は「白無地・和封筒(長形4号)」が基本
- 色: 白無地を選びます。茶封筒(クラフト封筒)は事務用なのでお礼状には使いません。
- 形: 縦長の和封筒が基本です。
- サイズ: B5便箋を三つ折りにするなら「長形4号」、A4便箋なら「長形3号」が適しています。
- 紙質: 中身が透けないよう、二重になっているタイプ(二重封筒)が最適ですが、厚手のものであれば一重でも構いません。
【図解】表面(宛名)と裏面(差出人)の正しい配置
文字のバランスは「相手を大きく、自分を小さく」が鉄則です。
- 表面(宛先):
- 住所: 右端に、郵便番号枠から一文字下げて書き始めます。都道府県から省略せずに書きましょう。
- 学校名: 中央よりやや右に書きます。
- 宛名: 中央に大きく書きます。「校長 〇〇 〇〇 先生」や「指導教諭 〇〇 〇〇 様(または先生)」など。
- 裏面(差出人):
- 住所・氏名: 封筒の継ぎ目(センターライン)の左側、または継ぎ目を挟んで右に住所、左に氏名を書きます。
- 大学名: 自分の氏名の横(または上)に、大学・学部・学科を必ず記載しましょう。「誰だっけ?」とならないための配慮です。
「朱書き(教育実習御礼)」はどこに書く?
封筒の表面、左下の空いているスペースに、赤ペン(定規を使って丁寧に)で「教育実習お礼状在中」または「御礼」と朱書きします。
これにより、学校に届いた膨大な郵便物の中で、事務職員の方が「実習生からの手紙だ」とすぐに判断でき、スムーズに先生の手元へ届きます。
お礼状を出すタイミングと投函方法
手紙は鮮度が命です。実習が終わった解放感で後回しにしないようにしましょう。
実習終了後「2〜3日以内」に出すのが鉄則
お礼状は、実習終了日の翌日、遅くとも3日以内には投函するのがマナーです。
1週間以上経ってから届くお礼状は、「形式的に出したんだな」と思われてしまいます。実習中の熱意が冷めないうちに送りましょう。
ポスト投函よりも「郵便局窓口」をおすすめする理由
確実に届けるためには、ポスト投函よりも郵便局の窓口へ持っていくことをおすすめします。
- 理由1: 料金(重さ)の最終確認ができる。
- 理由2: 消印がきれいに押される(ポスト投函だと稀に汚れたり、集荷の時間帯によっては翌日扱いになったりする)。
- 理由3: その場で記念切手を選んで貼れる。
複数の先生に送る場合「まとめて封入」はアリ?
原則は、校長先生、教頭先生、指導教諭など、一人ひとりに個別の封筒を用意して送ります。
ただし、教科指導でお世話になった他の先生方などへ送りたい場合、個別に住所を知らないことも多いでしょう。その場合は、指導教諭宛の封筒の中に、他の先生宛の手紙(封筒に入れた状態のもの)を同封し、「〇〇先生へお渡しいただけますでしょうか」と添え状やメモをつける方法もあります。
しかし、基本的には「校長宛」「指導教諭宛」の2通は必須とし、それぞれ郵送するのが最も丁寧です。
よくある質問(Q&A)
Q. 110円切手が手元にない場合、少額切手を複数貼ってもいい?
A. マナー違反ではありませんが、お礼状としては避けたほうが無難です。
切手を何枚も貼り合わせると、「寄せ集め感」が出てしまい、相手に対する敬意が薄れて見えます。どうしてもという場合を除き、110円切手1枚を用意しましょう。
Q. 封筒の宛名は「行」を「様」に書き換えるべき?(返信用封筒)
A. 自分が送る封筒には最初から「様(先生)」を書きます。
もし、実習校から自分宛てに返信用封筒を送ってもらうような場面(書類のやり取りなど)があれば、自分の名前の下の「行」や「宛」を書き、相手が送り返す際に「様」に直してもらいます。しかし、今回のお礼状はこちらから一方的に送るものなので、最初から敬称(校長 〇〇 先生、〇〇 様)をつけて書きます。
Q. 書き損じたら修正テープを使ってもいい?
A. 絶対にNGです。
宛名書きで間違えてしまった場合は、新しい封筒に書き直してください。修正テープや二重線での訂正は、目上の方への手紙では大変な失礼にあたります。予備の封筒を数枚用意しておくと安心です。
まとめ
2025年現在、教育実習のお礼状に貼る切手は「110円」です。
- 料金: 封書(50g以内)は一律110円。
- 切手: 季節の記念切手がベストだが、普通切手でもOK。キャラクターは避ける。
- 封筒: 白無地の和封筒(長形4号など)。宛名は丁寧に、朱書きを忘れずに。
- タイミング: 実習終了後、2〜3日以内に投函。
たかが切手、されど切手です。正しい料金ときれいな封筒で届いたお礼状は、あなたの「教師になりたい」という真剣な想いを、言葉以上に強く伝えてくれるはずです。