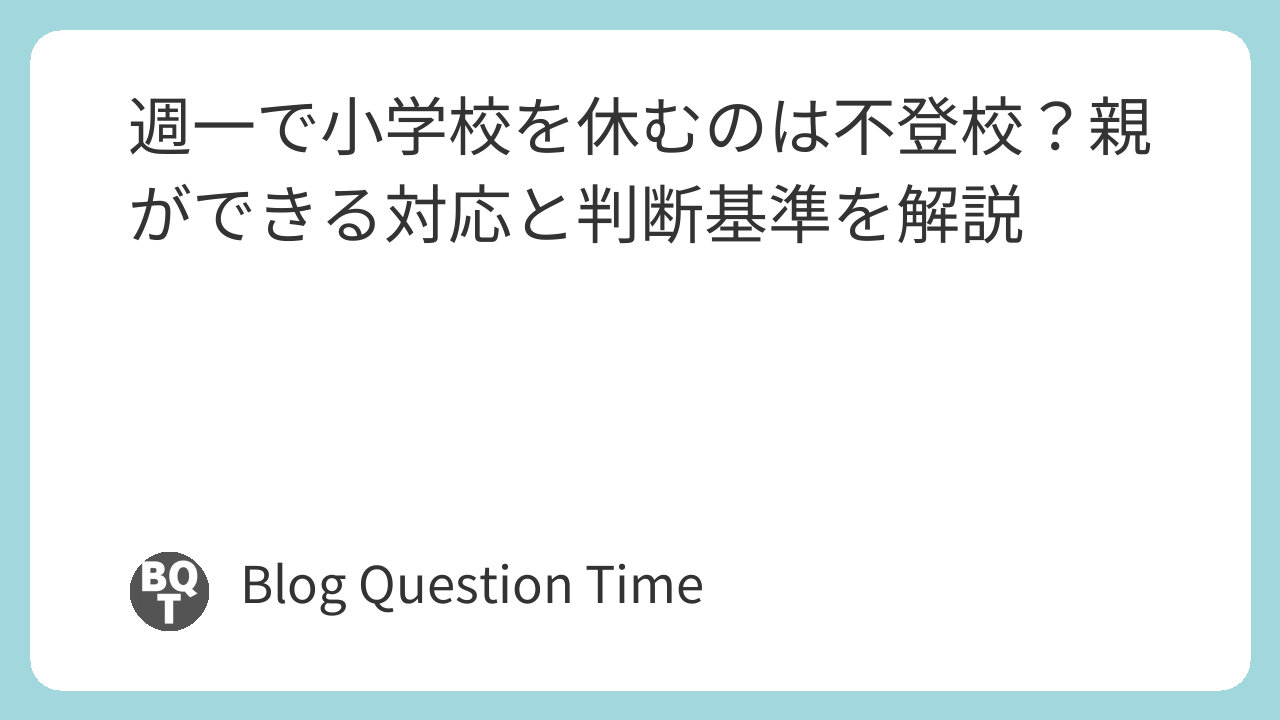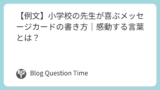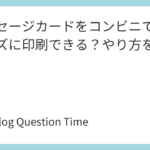朝、子供が「お腹が痛い」「学校に行きたくない」と布団から出てこない。週に一度のペースで休ませているけれど、これって甘やかしすぎ?もしかしてこのまま不登校になってしまうの?
そんな不安と罪悪感で、親自身の心が折れそうになってしまうことは珍しくありません。周囲の「無理にでも行かせなきゃダメだよ」という言葉に、さらに追い詰められている方もいるでしょう。
この記事では、週に一度学校を休むことの法的な定義から、子供の心に隠れたサイン、そして親としてどのように向き合い、状況を改善していくべきかの正解を徹底解説します。
週一の欠席は不登校の定義に当てはまるのか
まず、多くの親が恐れている「不登校」という言葉の定義を整理しましょう。
文部科学省の定義では、年間30日以上の欠席を「不登校」としています。
小学校の年間授業日数は約200日程度です。週に1回休むペースが1年間続くと、欠席日数は約35〜40日に達します。つまり、数字の上では立派な「不登校」の範囲に含まれることになります。
まずはこの現状を「やばい」とパニックになるのではなく、「うちの子は今、支援が必要な状態にあるんだ」と冷静に受け止めることが、解決への第一歩となります。
なぜ週に一度なのか?子供が発しているサインの正体
毎日休むわけではなく「週に一度」というリズムには、子供なりの理由が隠されています。
本人も理由が分からないエネルギー切れの状態
大人でも、仕事のストレスが溜まると「今日はどうしても無理だ」と感じる日があります。子供の場合、学校という集団生活の中で常に神経を張り巡らせており、そのエネルギーが切れてしまうのがちょうど「週の半ば」だったり、休み明けの「月曜日」だったりするのです。
3年生の壁や5年生の荒れなど学年特有の要因
小学校3年生頃から学習内容が急に難しくなり、友人関係も複雑になります。また、高学年になると思春期の入り口に立ち、精神的な葛藤も増えます。こうした「成長の節目」に感じるプレッシャーが、登校渋りとして現れることがよくあります。
すぐ学校を休ませる親はダメ?2つの考え方を比較
「無理にでも行かせるべき」という意見と「休ませて様子を見るべき」という意見、どちらが正しいのか迷いますよね。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 方針 | メリット | デメリット | 向いている状態 |
|---|---|---|---|
| 必ず行かせる方針 | 規則正しい生活習慣が維持でき、忍耐力がつく。 | 子供が限界を超えてしまい、二次障害や完全な不登校を招く恐れがある。 | 単なる「朝の寝坊」や、一時的な「面倒くささ」の場合。 |
| 柔軟に休ませる方針 | 子供の心の安全を守ることができ、親への信頼関係が深まる。 | 学習の遅れが不安になり、集団生活への抵抗感が強まる可能性がある。 | 心身に明らかな疲労が見られる、強い不安や恐怖がある場合。 |
「すぐ休ませる親」というレッテルを気にする必要はありません。大切なのは世間の目ではなく、目の前の子供の状態に合った選択をすることです。
親が迷った時の休ませる・行かせる判断チェックリスト
朝のやり取りで判断に迷った時は、以下の項目を確認してみてください。
- 学校を休むと決めた瞬間に、腹痛などの体調不良が改善するか(心のサイン)
- 食欲や睡眠など、生活の基本となるリズムが大きく崩れていないか
- 学校の話題を出すと、極端に黙り込んだり泣き出したりしないか
- 「明日は行く」という約束を繰り返すが、当日になると動けないか
これらの項目に当てはまる数が多いほど、子供は「行きたくない」のではなく、心身のエネルギーが枯渇して「行けない」状態にある可能性が高いです。
状況を改善するための具体的なアクション
ただ休ませるだけでなく、状況を前向きに変えていくためのアクションが必要です。
あらかじめお休みの日を予約する
突発的に休むと、親も子も「また休んでしまった」という敗北感に襲われます。それを防ぐために、「水曜日はお休みの日にしよう」と事前に決めてしまう方法があります。
ゴールが見えることで「あと2日頑張れば休みだ」と見通しが立ち、結果的に他の4日間の登校が安定するケースも多いです。
学校やスクールカウンセラーを味方にする
担任の先生には、今の状況を正直に伝えましょう。「サボらせている」と思われるのが不安かもしれませんが、多くの先生は「週一でも通おうとしている頑張り」を認めてくれます。また、スクールカウンセラーという専門家を介することで、親自身の不安も軽減されます。
家を最高の充電場所にする
休んだ日に「勉強しなさい!」と怒鳴ったり、ずっとスマホを禁止したりして、家を針のむしろにしてはいけません。休んだ日はしっかりと心を休ませ、エネルギーを溜めることが目的です。親子の信頼関係を深める時間に充てることで、子供の「次の一歩」への勇気が湧いてきます。
学校を休むことに関するよくある質問
週一で休むと勉強に遅れが出ませんか
確かにその懸念はあります。しかし、今の時代はタブレット学習やオンライン教材、さらには「放課後登校」でプリントをもらうなど、学校以外の学習手段が豊富にあります。心さえ元気であれば、勉強は後から取り戻せます。
学校を休む癖がつくのが怖いです
「一度休んだら二度と行けなくなる」というのは極端な不安です。多くの不登校経験者は、エネルギーが溜まったタイミングで自ら動き出します。大切なのは「癖」を心配することではなく、なぜ今休む必要があるのかという「根本的な理由」に寄り添うことです。
周囲から甘やかしだと言われたらどうすればいいですか
外部の声には耳を貸さなくて大丈夫です。子供の心を守れるのは、親であるあなただけです。「今はこういう方針で、専門家とも相談しながらやっています」と毅然とした態度で答えましょう。
まとめ
週一で小学校を休むことは、データ上は不登校の入り口かもしれませんが、決して人生の終わりではありません。
- 現状把握: 週一の欠席は年間30日を超えるため、支援が必要なサイン。
- 判断: 体調や表情をよく観察し、無理強いが逆効果にならないか見極める。
- 対策: 「戦略的お休み」や学校との連携を通じて、家を安心できる場所に整える。
子供が発しているサインを無視せず、共に歩んでいく姿勢を見せることが、一番の特効薬になります。親も適度に肩の力を抜き、自分自身のメンタルケアも大切にしてください。